玉川という「河川名」
「玉川」という河川名の成り立ちは、一例をあげれば「田間」を玉としたような土地に根ざす要因や、「玉造部(たまつくりべ)、古代に勾玉(まがたま)や管玉(くだたま)などの玉類を製造する人たちがいた」「霊魂の「たま」をひそませた霊水を感じさせる」「屯田の開拓民がつけた故郷の川名」など歴史や神聖さを感じさせる要因などもあると聞けば、この単純な二文字には力が籠っているようにも思え、尚且つ玉川学園の創設者「小原國芳」さんの「わかりやすく、書きやすい、感じがよい」という学園名選択の考え方も清々しく、印象をより良くさせている。
① ウィキペディアに掲載されている各地の「玉川」
一級河川
秋田県大仙市・仙北市を流れる雄物川水系。山形県西置賜郡小国町を流れる荒川水系。福島県大沼郡昭和村を流れる阿賀野川水系野尻川支流。茨城県常陸大宮市を流れる久慈川水系。千葉県香取市を流れる利根川水系黒部川支流。神奈川県厚木市を流れる相模川水系。長野県飯田市を流れる天竜川水系イタチ川支流。京都府綴喜郡井手町を流れる淀川水系木津川支流。京都府福知山市を流れる由良川水系宮川支流。鳥取県倉吉市を流れる天神川水系小鴨川支流。島根県江津市を流れる江の川水系八戸川支流。岡山県高梁市を流れる高梁川水系。愛媛県大洲市を流れる肱川水系。神奈川県厚木市小野近辺の相模川水系。
二級河川
北海道古宇郡泊村を流れる本流。新潟県佐渡市を流れる本流。和歌山県日高郡みなべ町を流れる南部川水系。和歌山県有田郡有田川町を流れる有田川水系早月谷川支流。香川県坂出市を流れる本流。愛媛県今治市を流れる蒼社川水系木地川支流。
指定区間外
青森県東津軽郡外ヶ浜町を流れる本流。山形県東田川郡庄内町を流れる最上川水系立谷沢川支流。
その他
ロシアが実効支配しているサハリン州南部(旧南樺太)ユジノサハリンスク市(旧豊原市)北部を流れるロガトカ川の旧日本統治時代の旧称。関東地方を流れる多摩川の別表記。地名、団体名などに用いられる。玉川上水、多摩川より取水し、江戸へ供給していた上水道。
「玉川」という名の川は全国に100を超えるという説もあるが、「川の名前を調べる地図」というサイトによると「須玉川」「氷玉川」「三玉川」「目玉川」「小玉川」「真玉川」「久玉川」「矢玉川」「湧玉川」「戸玉川」「御玉川」「湯玉川」「白玉川」「垂玉川」「玉川川」のような各地の事情が勘案されたような変則が見られ、こうしたものも含まれているのかも知れない。全部面白くて抜き書きしたが、最後の「玉川川(たまがわがわ)」は誤植を疑いサイトの深掘りをすると、福井県の丹生郡越前町玉川を流れる二級河川で、おそらく玉川の地を流れる川という命名のようだ。

北陸自動車道米山PAから見た「佐渡島」。二子塚があるとすればこんな形に見えるのだろうか。「玉川」はおそらく左側の「大佐渡山地(見えている側に金山跡がある)」の裏側(見えない方向)に流れている。北陸自動車は300年前の松尾芭蕉「奥の細道」紀行の北陸ルートに重なり、各サービスエリアに「句の碑」がある。
草臥(くたぶ)れて 宿(やど)かるころや 藤の花
② ウィキペディアから拾った「六玉川(むたまがわ)」
歌枕(うたまくら)、現在はもっぱら和歌の題材とされた日本の名所旧跡のことをさしていう。以下の六つは全国にある歌枕に使用される玉川で、あわせて六玉川(むたまがわ)と呼ばれる。
野路の玉川(のじのたまがわ) : 滋賀県草津市野路町
明日もこむ 野路の玉川 萩こえて いろなる波に 月やどりけり(『千載和歌集』、源俊頼)
野田の玉川(たまがわ): 宮城県塩竈市と多賀城市を流れる川で砂押川の支流
夕されば 潮風越して みちのくの 野田の玉川 千鳥鳴くなり(『新古今和歌集』、能因法師)
調布の玉川(たつくり(てづくり)のたまがわ) : 東京都を流れる多摩川、調布市、田園調布(ちなみに調布とは「租庸調」の「調の麻布」のこと)
多摩川に 曝す手作り さらさらに 何そこの児の ここだ愛しき(『万葉集』、東歌)
井手の玉川(たまがわ): 京都府井手町を流れる玉川
駒とめて なほ水かはん やまぶきの 花の露そふ 井手の玉川(『新古今和歌集』、藤原俊成)
三島の玉川(たまがわ): 大阪府高槻市
見渡せば 波のしがらみ かけてけり 卯の花咲ける 玉川の里(『後拾遺和歌集』、相模)
高野の玉川(たまがわ): 和歌山県高野山
わすれても 汲みやしつらん 旅人の 高野の奥の 玉川の水(『風雅和歌集』、弘法大師)
(玉川の川名を尋ねる面白い作業だった)
「玉川温泉」に行ってみた
私の住む「玉川」の地名は、近くを流れる「多摩川」の美称を採用したというのが通説だが、ふと全国には「玉川」という地名がどのくらいあるのか気になり、手元にあった国際地学協会作製の日本地図(索引込みで100ページの硬本)の索引(全国市町村名)で調べてみると、愛媛(町)、福島(村)、埼玉(村)の3ヶ所だけだった。これを押さえて、予約していた「同名」の玉川温泉に出かけた。暇はあるから簡単に検索できそうという腹づもりだった。
玉川温泉【秋田県仙北市田沢湖玉川渋黒沢】
地獄谷は天然記念物の「北投石」が自然に生成する希少な所、近くの源泉が噴出する湯の川沿いの、地面の温かい場所を選んで天然の岩盤浴が出来る。たくさんの人が茣蓙を敷いて毛布を被って寝転んでいて、戦争とか災害の被災地と見紛うと言ったら大袈裟だが、荒涼とした地獄谷に点々と人が「転がっている」状態からは、一瞬各々の切実感のようなものが伝わってくる。単なる健康志向もあるのだろうが、自然のラジウムが感じられる?あの世のような世界観の中で、何らかの障害の克服を願っている人もいるだろう。大地に直接寝転ぶという前近代的でてらいが少しも見られない光景が繰り広げられている。宿の人には専用の屋根付きの場所があり、一般の人は暖かくなっている場所を各自で探すことが求められ、早い者勝ちだから、十分な熱量の無い場所で寝転んでいる人もいるような感じがする。地熱の発汗作用で何らかの治療、リラックス効果が期待されているようだ。

左:源泉から噴き出した高温の「湯の川」が旅館の施設に向かっていく(途中に湯畑がある)。温泉宿全体が湯煙の中に包まれ、地獄谷全体から湧き上がる大量の湯煙は、少し離れた山影からも雲が湧いているかのように見える。(帰りがけに、幾つかのトンネルを過ぎ振り返ると、周辺の青空の中で一か所だけ真っ白い雲が湧きたっているところが見える)中:地獄谷には散策道があり、コンクリート敷きの平面で熱伝導が良いのか左右に人も多い。右:谷の入り口小高い所に小さなお社があり、玉川薬師神社の表札は「源泉地帯の毒気」に滲んでいる。
私は戦場のような川一帯は人を避けながら散歩しただけで、専ら強酸性のお湯に浸かり(一日2回まで、一回15分までと脅かされた)湯治の初心者ルールを守って、後は読書三昧。宿の人の話では偶に、長湯して変調をきたし救急車のお世話になる例があり、一番早くても到着に45分はかかるとのことで、それだけ強い湯なので「お互いの為」に敢て強調しているようだ。
奇跡の魚「クニマス」
「玉川」という名前なのだから村でもあるのかなとネット検索したら、「玉川」という川の名前から来ているようだ(自分の住む玉川と一緒だ)。温泉の近くに流れるのは「渋黒川」で、10km位下流で玉川に合流している。直近の「渋黒川」ではなく、なぜ10km離れた「玉川」なのかだが、渋黒川はあくまで支流で田沢湖に流れ込むのは本流の「玉川」で、途中に玉川ダムもあり存在感のある名前、更には「涼やかな」印象として選択されたようだ(あくまでも想像)。
検索していて分かった事は「玉川」は玉川毒水とも呼ばれ、川の水が流れ込む「田沢湖」のみに生息していた「クニマス」を全滅に追い込んでいる。昭和15年(1940)の事で灌漑と水力発電のためにクニマスは犠牲となった。(十分な中和ができず、作物や発電機器を守る為に玉川の塩酸を多く含む酸性水を、直接田沢湖に流し薄めた)何年か前、有毒ガスが発生して温泉が一時閉鎖されたというニュースは記憶に新しいし、実際に行ってみると有毒ガスの発生しやすい地点の地図や、発生を知らせる警報装置も要所々々に点在している。
幻の「クニマス」は70年の時を経て、突如富士山に出現した。クニマスの卵が昔、各地に移植され、その内の「西湖」(富士五湖の一つ)では存在すら忘れられていて、地元では絶滅種と知らずに捕獲していたが、平成22年(2010)になって漁業団体が「さかなクン」を頼って「個体」を届け、さかなクンが関係機関に手配しその生息が確認された。今では西湖が田沢湖に代わって世界唯一の生息地であり、西湖の環境保全計画がすすめられている。
「“絶滅”した幻のクニマスを発見」の情報が温泉に浸かりに行って、そうか「ここだったんだ」と感慨を深める機会を得るという思いもよらない機会だった。いくつかのニュースを、その実際の現場で理解を深めることになるとは思いもしなかった。
各地の地名としての「玉川」

瀬田・玉川には、戦国時代の終わりごろに定着したと言われている「長崎」を名乗る表札が良く見られる。私がブログを通して推察していることだが、三島近辺に「長崎」という地名があり、鎌倉時代から長崎氏は時代々々に登場するので、この地が本拠地だったと推定している。この長崎という地の近くに「玉川」という地名があり、直ぐ近くに有名な富士山一帯の湧水地の一つ「柿田川湧水群」がある。残念ながら川に由来した名称では無いようだ。
宿で寝転びながら暇に飽かせて、「玉川」「玉川村」で検索していた。幸い“Wi-Fi”が完備されていたので大いに助かる。キャリアが楽天なので、直接の電波受信など夢の夢だったことは間違いない。
●岩手県九戸郡野田村「マリンローズパーク野田玉川地下博物館」
野田玉川鉱山は日本有数のマンガン鉱山として栄えた。含有量の少ないピンク色の鉱石を「バラ輝石」と呼ぶ。地図で確認すると「玉川」という川が存在し、下流の海沿いには「野田玉川」という駅もあり、近くには「玉川地区農業集落排水処理場」という施設が見えるので、地名(字(あざ)名)ようだ。
●福島県石川郡玉川村
ネットで検索すると様々な項目が出てくるので、活動が盛んな村のようだ。昭和30年(1955)二つの村が合併して「玉川村」になっているが、その由来は見つけられなかった。町田の「玉川学園」と協力関係があるという情報には奇縁を感じた(上述、河川名の前説との関係)。
●埼玉県比企郡玉川村
明治22年(1889)4ヶ村が合併して「玉川村」となる。
平成16年(2006)2ヶ村が合併して「ときがわ町」となる。
行政としての玉川は無くなったが、玉川の地名・施設名は随所に見られる。中心地に玉川の地名があり、それが由来だったのかもしれないが、ゴルフ場も温泉も見事にみんな「玉川」を名乗っている。
●多摩源流の郷「玉川キャンプ場」
様々なログハウスとオートキャンプ場を備えている。奥多摩湖の上流、山梨県北都留郡小菅村に位置し、キャンプ場は小菅川に「玉川」が合流する地点にある。「川ではヤマメ.イワナやニジマスを放流しているので、釣り放題!」という謳い文句がホームページにあるので、名前の由来は「玉川」を有効活用しているということのようだ。
多摩川の上流に「玉川」が存在する。「丹波川」と「小菅川」が合流して奥多摩湖(小河内ダム)になり、ダムから下流が「多摩川」になる。と、ここまで来て全国で町村が3ヶ所?という情報への疑問が湧いてきた。玉川を入力し表示された情報を次々開き、内容は限られるので地図などを見ながら周辺に川があるか、施設等はどうか、スマホではきつい作業なので、気楽に考えていたスマホ検索を止め、読書に切り替える。しかし町村は3ヶ所では済みそうにない。東京へ帰っての宿題。

閑話休題。玉川の名称から外れるが、住所で言えば代沢5丁目、一般的に知られている「下北沢」近辺に「二子橋」がある。笹塚から淡島通りまで通る「鎌倉街道(正式な地図名称)」が「北沢川緑道」と交差する所に鎌倉橋があり、その下流側に並んで「二子橋」はある。「代沢の二子橋」。鎌倉街道は淡島通りから先がどうなっているかは不明だが、淡島通りを右に折れれば、松陰神社から用賀へ向かう道筋があり、「玉川の二子橋」を渡って鎌倉へ向かったのかも知れない。
1997年版の「日本地図」
この本の索引には、各県全図に記載されている市町村名は全て音訓順に配列したと記載されている。調べてみると、この当時の市町村数は3255(ちなみに現在1741)、索引は1~18ページで各ページ一列64行、4列構成となっている。「あいうえお」の項目表示に平均10行以上取ってあるので、全国の市町村数は網羅されているような感じはするが、帰宅後、PC画面で調べてみると、各地に地名を含めいくつもの市町村があることが、下記のとおり分かった。
これは「日本地図」が間違っているのではなく、市町村合併が繰り返し行われてきたので、各情報の年代の食い違いが生じているということのようだ。静岡県安倍郡玉川村のような昭和44年(1969)静岡市に編入され玉川村は廃止されているので、当然97年版には記載されない。又、金沢市立玉川図書館が有名?な石川県金沢市玉川町などは現存する町名だが、「県全図」に記載されているという前提では、大都市の町名は地図には記載されていないので、索引にも記載されていないということのようだ。
玉川の名称を調べていたら、こんな所まで漂いネットの海で溺れそうになっている。得られた教訓は、図書には製作意図が明確にあり、偶々本を手にしてそこで得られた情報を鵜呑みにしてはならないということで、私がぬか喜びした全国で玉川町・村は3ヶ所というという「間違い」、上述の河川名で見たようにネット情報は複数のサイトを巡る大切さ。そしてぎりぎりまで断定はしないような思考が求められると思う。
正確さを期すなら専門書や研究資料等があり、私のような玉川の地名、名称への好奇心程度なら、幅広な情報を整理して朧げな像を浮かべてみるというのも一興である。
その他の町村や地名等
●鹿島玉川神社(青梅市)
境内に巨大な神石あり、このためここを清地として、承平のころ、源経基が常陸の鹿島神社を勧請したといわれ、もと、鹿島社とか、鹿島大明神と称した。玉川明神は、明暦のころ、玉川上水の清浄を祈願したのがはじめといわれている。
●静岡県安倍郡玉川村(たまかわむら)
安倍川支流の中河内川流域の村。由来は古くから玉川郷と呼んでいた事による。明治22年の町村制により、周辺15ヶ村を以て新たに「玉川村」とした。昭和44年(1969)静岡市に編入され玉川村は廃止された。比企の玉川村同様、学校名や施設・企業名に「玉川」の名称は生きています。
由来の説明があるところ
大阪府中河内郡玉川町(現・東大阪市)
かつては西は楠根川(現・第二寝屋川)、東は菱江川(玉串川の分流)に挟まれた低湿地であり、たびたび水害に遭っていた。水害はあるも、川に挟まれた地域であったため、全国に点在する玉川の地名から見られるように、「美しい」を意味する「玉」という接頭語を「川」につけた地名になったと推測されるが、天平勝宝6年(西暦754年)に風雨を治めるために、玉櫛笥(たまくしげ)を旧大和川上流より流し、津原(現在の花園本町)の池にたどり着いたことから名付けられたとされる「たまくし川」が地域の東にあったことから、「たま川」とされたとも考えられる。(美しい地名の由来に出会った)
1889年、町村制施行に伴い各村が合併して若江郡玉川村が成立。
愛媛県越智郡玉川町(現・今治市)
町の中央部を二級河川の蒼社川が流れている。中流域には玉川ダムがあり、蒼社川は今治市の上水道としての役割を担ってきた。
昭和29年(1954)鈍川村、九和村、鴨部村、竜岡村が合併して玉川村となる。
玉川は玉川町の中でもっともゆるやかでのどかな川。伊勢神宮の所領(玉川の御厨(みくりや))があったので、合併時に統合の名前の由来となった。(ゆるやか、のどか、神宮のみくりや豊かさが想起される)
その他の地域
山形県鶴岡市羽黒町玉川、福島県いわき市小名浜玉川町、東京都昭島市玉川町、石川県金沢市玉川町、愛知県名古屋市中川区玉川町、岡山県高梁市玉川町、福岡県福岡市南区玉川町、大分県日田市玉川町
町丁・大字
北海道中川郡美深町の字、岩手県九戸郡野田村の大字、宮城県塩竈市の地名、山形県西置賜郡小国町の大字、埼玉県比企郡ときがわ町の大字、東京都世田谷区の町名、東京都羽村市の地名、福井県丹生郡越前町の地名、山梨県都留市の地名、山梨県甲斐市の地名、長野県茅野市の地名、静岡県三島市の地名、静岡県駿東郡清水町の地名、三重県度会郡玉城町の地名、大阪府大阪市福島区の地名、大阪府高槻市の地名
渋谷・道玄坂の二子(ふたご)と玉川

最後のおまけ。渋谷駅を出て道玄坂を上って坂上を過ぎた所で、写真の2軒は向かい合うように存在している。道玄坂を多摩川に見立てると、まるで、ここに二子玉川が再現されているようにも見える。川下(渋谷駅)から見ると、左に「ふたご(二子:川崎側)」、右に「玉川(東京側)」がある。この配置関係から密かに道元坂上の「二子玉川」と呼んでいる。偶然にしても出来過ぎ。


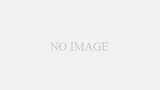
コメント