「多摩川」を挟んだ二つの村 ②
弟(妹)たる「瀬田」そして玉川
荏原郡とその後
この地域は古くは「荏原(えばら)郡」と呼ばれ、「新編武蔵風土記稿」によれば、奈良時代に荏(荏胡麻)が繁茂していたため、「荏の原」と呼ばれたことを由来とする説明がなされている。地域的には、目黒・大田・品川のほぼ全体と世田谷・港・千代田の大部分を占めていたが、江戸時代になると江戸御府内は荏原郡からはずれ、六郷(34村)・馬込(13村)・世田谷(30村)・品川(13村)・麻布(5村)の5領となった。
更に、明治22年(1889)の町村制の施行では1町18村となり、唯一の「町」は都心に近く(人口が多い?)、「宿場町」でもあった品川だった。玉川村は世田谷に含まれ、八つの村と三つの地域で構成された。(尾山村、奥沢村、等々力村、用賀村、瀬田村[大部分]、野良田村、上野毛村、下野毛村[大部分]、深沢村[一部]、衾村[飛地]、下沼部村[飛地])
昭和7年(1932)の改正では「郡制」に変えて東京市となり、区制が採用され全6区の内の「世田谷区」は世田ヶ谷町、駒沢町、玉川村、松沢村で構成されている。この時期、玉川村では後に歴史に名を刻む、住民主体の大規模な「全円耕地整理事業」が進行中であり、自立の気概も高く「玉川地区独立の建議書」を区会に提出するだけでなく、その後も粘り強く働きかけていたが、昭和22年(1947)には却下されてしまう。これを受けて村内各地域は「町」に移行するに当たり、町名の頭に「玉川」を付け、却下されても尚、まるで独立の気概を示すような決着をさせた。旧瀬田地域は「玉川瀬田町」と「玉川町」に分けられましたが、深慮のあるなしに関わらず、このことが玉川村の「自主独立」の遺伝子を、「玉川町」という村内の辺境の地、「人が住むに能わず」とされてきた土地に集約させたのかもしれない。(名は体を表す)

昭和30年頃の瀬田周辺の地図。少し見難いが、玉川の冠が町名にのっている
玉川冠の町名は、昭和43年(1968)頃の住居表示制度実施まで続き、「旧玉川村」に由来する地名は、純粋培養的な「玉川町」の他に、大田区との境に「東玉川町」と「玉川田園調布」が残されている。
瀬田の小歴史
瀬田の地名由来
諸説あるが「瀬戸」が転訛(てんか・なまり)したという説が有力と言われ、本来は「狭小な海峡」の意味ですが、いつしか海がなくても狭い谷地を「瀬戸」と言うようになったようだ。確かに村の中心を南北に貫く「現、上野毛通り」は、国分寺崖線の「稲荷坂」を下ると直ぐ多摩川の沿岸だったようなので、頷けるところがある。昭和30年代まで崖下には、多摩川の存在を感じさせる東西200mの淵が「明神池」として残り、東急が渋谷駅北口の「東急文化会館」を建設する際の残土で、埋め戻したとの噂も耳にするので、外形的にも実証されると思う。(上記は、現代の地形を基準に判断しているが、稲荷坂は見るからに切通しのようなので、古い地形を考慮すると、もう一つ上流側の「現、駒沢通り」のまむし坂が、名からくる雰囲気のどおり「谷戸」なので当該地だとして、明神池の存在で多摩川が崖下に近かった点が重要と考え、説明に利用した)
「崖下」は洪水が多発し、古墳も人も「崖上」が生活の基盤
崖下は現、玉川1~4丁目、上野毛2~3丁目(一部)、野毛3丁目(半分)で、崖上は現、瀬田1、2、4丁目、上野毛2~3丁目、野毛3丁目であり、時代がだいぶ進むが、地元の名家、長崎佳久氏は以下のように回顧されている。
「当時は、玉川税務署辺が桃畑で、西は谷川の先に農家が若干あっただけで、その間は一面の田畑で家は一軒もなかった。もっとも南の、今の富士館会館辺は茶屋が10軒ほど並んでいて鮎のとれる夏は賑わった。しかしそのすぐ裏の、今の高島屋辺になればもう平凡な農村風景に戻っていた。」
「この田畑の耕作者は皆、北の高台に(今の瀬田)に住んでいて、始終次太夫堀を越えては耕作に出た。」
ある意味、後に登場する「玉川町」は水害多発地域として、繰り返すが「住むに能わずの地」だったようで、農業面でもリスクの大きな生産地帯だった事は間違いなく、この地が僅か半世紀程後、みるみるうちに価値を生み、地域全体を大きく発展させる起爆地域になるとは、当時、誰が想像できたことだろう。

玉川3・4丁目中心だが、昭和20年~25年頃
武士たちの時代から、土地の価値は早くから見極められていた
広い関東平野は、平安の都から皇室を離脱(臣籍降下)した皇族が割拠し、狭い都から解放された皇族たちは、平氏や源氏を名乗って、のびのびと勢力の拡大に励んできた。こうして「一所懸命」を旨に、自らの力を蓄えた武士たちが、やがて鎌倉に幕府を興し、数限りない戦いの明け暮れから、徳川の時代に至っている。(徳川家康は源氏の「新田氏」を名乗っている)
世田谷の「殿様」といえば、地域の住人なら誰でも「世田谷城主・吉良氏」を思い浮かべると思う。元々は足利尊氏(たかうじ)の一族の三河・吉良氏の流れで、南北朝時代、奥州管領として足利政権を支えたが、「観応の擾乱」以降、衰退の一途となり、初代鎌倉公方の基氏(もとうじ、足利尊氏4男)の誘い(救いの手)にのり、上野(こうずけ、群馬)から最終的には世田谷に所領を得た(一説には1450年頃とされている)。(世田谷城の説明では、貞治5年(1366)に所領を得たとされているが、基氏の在職が(1349-1367)なのと上野の扱いが考慮されていないので事実関係は微妙です)
いずれにしても室町時代以降、世田谷を体系的に支配したのは、「世田谷殿」とも呼ばれた武蔵・吉良氏であり、「瀬田」も吉良氏の領地に含まれ、瀬田・上野毛には吉良の家臣(らしい)も定着している。その吉良氏も、1550年頃の関東の複雑な合従連衡に疲れたのか戦いの一線から身を引き、その頃関東の覇者に名乗りを上げていた「後北条氏」の風下に立った。後北条氏二代当主・北条氏綱(うじつな)の娘を正室に迎え、足利氏の流れを汲む「鎌倉公方の御一家」という別格の扱いを受けていた。

世田谷区内唯一の歴史公園。世田谷城址公園は、東京都指定文化財に指定されている
長崎氏という名主
天正18年(1590)豊臣秀吉の小田原征伐で後北条氏は滅亡するが、その20数年前には長崎重高(しげたか)など8名の家臣が瀬田に定着する。長崎氏の移住は家人等11名とされているので、その家族や下僕等含めれば総勢は数十人だったかもしれない。この時に同時に、烏山・弦巻・宇奈根・北見・小机・深沢・用賀と同じく北条の家臣団が下向しているので、将来の波乱を予想して、恐らく吉良氏の監視という役割があったのではないかと推測している。
一概には言い切れないが、多摩川と国分寺崖線は関東と相模を分ける重要な要衝だったようだ。通説では、長崎氏が「瀬田城」を構築したと言われているが、指摘されている「レモン型」の台地に移り住んだのは、主家滅亡後約50年後の孫の世代のことなので、もう徳川の直轄地の時代であり、私としては「城」説はとらず、館を城としていたような気がする。後北条氏の家臣であった長崎氏は、その後は土着して帰農し瀬田村の名主となった。今もその館跡に「長崎館」の石柱が残されている。
長崎氏に関して天明6年(1786)の彦根藩の記録では、世田谷領内の名主の「持高」が、世田谷村名主二人、37石。岡本村17石。大蔵村31石。上野毛村21石。下野毛村13石、野良田村16石。宇奈根村60石。そして瀬田村「長崎四郎兵ェ」71石となっていて、群を抜いていることから相当大きな土地を所有していたと推定され、後年、子孫の方は「おじいさんが自分の土地を一日では回り切れなかった」と回想している。
瀬田は、北条家が事前に家臣を配置した上で、その位置関係から見ても中心にあたり、いざという時は長崎氏が全体のまとめ役だったという推測もなされる。幸い、横浜の蒔田城(まいた)で控えていた吉良氏も、世田谷方面も合戦に巻き込まれることなく、無事に徳川の治世に納まって行った。
大山街道に関する簡単な考察
瀬田は実態として、宿場でもなく純農村で、江戸時代の話題として「治太夫堀の開削」「徳川将軍の御成」、明治時代の「二子の渡し、経営」「青梅からの筏流し」、大正にかかっては「砂利の採掘」「別荘地と奉公」などの話題もなくもないが多くは地域共通の出来事で、地域全体を含めて純然たる農村地域を形成し、商業等の発達は限定的だった。
江戸時代から明治・大正までの瀬田は、地域的な特性(主に自然環境)からある程度の輝きも見られたが、古来より府中街道の宿場町として栄え、江戸時代に通行量の増した大山街道(矢倉沢往還)の渡船場・要衝として、幕府から宿場町の「継立の役割」を任せられた二子・溝ノ口が一段、格上で、地域の経済体制の確立という点において、多摩川を挟んで同じ街道筋として好対照で比べるべくもなかった。
両岸を南北に貫く大山街道も、現在でも旧道を歩くと川崎側の古街道らしさの重厚は、瀬田・玉川と比べるのが申し訳ないような気持ちになるが、東京側にもそれなり歴史はあるので、簡単なまとめを試みたい。街道には公用と私用の性格があり海岸際とか山道など通路が限られる所や、平地などでは通路が幾筋に分かれるような場所も見られる。おそらく公用の通路は規定されていて、分岐している所は観光等を目的とした自由で私用の通路だったように思う。
世田谷の大山街道は三軒茶屋で分岐し、大きく分かれ用賀で合流すると、玉川台の延命地蔵で分岐し、南に向かって左が「行善寺道」、右が「慈眼寺道」と分かれている。(大山街道全図を見ても、ここの全体が「8の字」のような分岐は見られない)三軒茶屋の分岐に関しては、代官屋敷を含む通路があるので頷けるが、瀬田・玉川の分岐は距離2㎞弱、道同士の間隔は500m弱なので、これは一体どういう訳なのかと訝しむが、「大山街道は行善寺側が本道だ。」という意見もあることから察すると、行善寺には徳川将軍の御成があり、長崎館がお休み処となった事を踏まえれば「公用道」だったように思う。そこは今の表現で言えば「都心」に向けて、川崎側から生産物や様々な物資が運ばれ、帰りには多少、時代がまぜこぜになるが肥料となる「下肥」が行き交ったとすれば、行善寺坂に「行火(あんか)坂」が付随するのも、体がポカポカになるという説明を裏付けるような気がする。
瀬田側には「二子の渡し」乗降場の形跡が2ヶ所あり、行善寺道の河原には標柱も立っている。馬や荷物を満載した舟を水平に渡すよりは、上(かみ)から斜めに渡す方が効率的で、ロープを通し引っ張っていたという記述もあるので、こうした推理ができるように思える。(流量により乗降場が変わったというだけで、具体的な渡船の仕方の記述は今の所分りません)
一方、慈眼寺道にはお寺が5ヶ寺(昭和初期移設の玉川寺含む)、神社3社(河岸の諏訪神社含む)があり、明らかに私用の観光道の体裁があり、人々は匂いを嗅ぎ分けるように道を作っていった証なのかも知れない。逆に人が通行するようになって社寺が出来たのかも知れない。ただ、長崎氏がこの街道沿いに拠点を築き、慈眼寺、御嶽神社(現、玉川神社)を崖上に勧進しているので、当時は鎌倉道だったのだろうが街道としての道筋は存在したようだ。
いずれにもせよ今日、行善寺道にしても、慈眼寺道(現、二子玉川商店街)にしても、江戸の人口100万人の内の20万人が、一年中行き交ったという当時の様子を窺えるような痕跡は見られない。

左:行善寺坂 中:二子玉川商店街 右:大山道フェスティバル「灯籠」
瀬田・玉川の文明開化 玉川電気鉄道(玉電)の企業努力
行楽地として恵まれた自然を見逃さず、農地だけという土地がかえって有効となり、明治40年(1907)「玉川電気鉄道」の開通が瀬田・玉川発展の端緒であり、住民があれよあれよと見守る間に、明治42年(1909)「玉川遊園地」まで開園し、地域にとっては降ってわいたような出来事であり、この事が結果的に長く続いた「二子(ふたご)と瀬田・玉川の兄弟のくびき」のようなものを解くこととなった。
困難を極めた営業開始まで
明治29年(1896)「玉川砂利電気鉄道」の名称で、「多摩川の砂利の需要が年々増えているので、馬力・人力では間に合わず、道路の渋滞への影響を小さくする」を目的に、玉川―三宅坂の間の鉄道敷設申請が提出された。この請願は14名の連名でなされていて、荏原郡在住者11名の中に、この地区からは上野毛の名主だった田中家の「田中筑閤(ちくご)」さんも含まれていた。
明治30年(1897)に「特許」は下りたが着手にいたらず、明治33年(1900)更に大規模な路線拡張計画を出願した(本来の「玉川線」に加えて「目黒線」「弦巻線」「調布線」(いずれも仮称)など一度不認可となった路線も含まれていた)が、不認可となってしまう。(14名が地域代表だったのかは分からないが、それぞれの主張が闘わされ迷走した様子が窺える)
明治35年(1902)内務省は、渡邊熊之進、田中筑閤、横溝清太郎の三名に対して、渋谷―玉川間の路線に対して「特許」を交付した。渡邊さん、田中さんは発起人14名の内で、横溝さんは急に登場している。この特許により、社名は「玉川電機鉄道」に改称され、田中さんは相談役の一人に名を連ねた。
明治36年(1903)会社創立総会が行われ、資本金40万円の「玉川電機鉄道株式会社」が設立したが、日露戦争期であり、東京府による街道の幅員拡張工事の用地買収と重なり、事業用地買収は難航し建設工事も停滞した。そこで土地収用事業の認定申請をし、公共の利益となる事業として土地収用法の認定を内務大臣から受けるが、同時期に警視庁及び東京府に提出した「電気鉄道工事施工認可申請」の認可は下りず。その為、「追願」として、東京府の予定改修道を外し三軒茶屋―玉川間の施工願いを提出し、明治39年(1906)正式に工事開始の認可が下りている。
この後、順調に推移したかと言えばそうならず、天候不順や工事業者とのゴタゴタや、渡邊取締役への批判が噴出、解任騒動に至り大幅に工事は遅延した。
慶応義塾人脈による再建
会社の信用は低下し、建設資金も株主からの調達は望めず借入金で凌ぐことし、責任を明確にする為「取締役は互選を以て社長及び専務取締役一名をおく」と臨時株主総会で定めて総会に臨み、借入案はなんとか容認されたものの、これまでの混乱の責任問題で紛糾し、経営陣の不手際もあり打開策も示せないまま散会となった。巨額な資本を必要とするインフラ整備事業を、資金的な裏付けのない者が計画し、遂行して来た無理が露呈することとなった。
この危機の時起業したばかりで、新町(桜新町)の住宅開発を計画していた「東京信託」から、優先株を発行することを条件に20万円の融資申し出があり、玉電は臨時株主総会でその申し入れを承認し、その結果、東京信託から専務取締役一名、取締役二名が就任した。こうして多難な10年間を経て、玉電はようやく開業の目途がたち、明治40年(1907)3月、道玄坂上~三軒茶屋間が開通し、続いて4月には三軒茶屋~玉川間が開通、8月には道玄坂上から渋谷までの全線が開通した。開業当日は、沿線地域に存在していた陸軍の半休日と重なったため、兵隊を中心に満員だったと言われている。
東京信託は新興とはいえ、東京市内の三井家の土地家屋の管理を任される程の実力があり、三井・三菱で勢力を誇っていた慶応義塾出身者が多数集まっていた。
開通以降
明治42年(1909)玉川遊園地開園(国分寺崖線沿い)。浅草花屋敷に運営を委託する。
大正11年(1922)玉川第二遊園地を開設(多摩川沿い)。
大正13年(1924)砧線開業
昭和2年(1927)溝の口延伸
昭和13年(1938)東京横浜電鉄に吸収される。その後、社名変更により東京急行電鉄となった。
昭和14年(1939)第二遊園地は読売新聞と提携し「読売遊園」と改称
昭和15年(1940)戦時体制下、地上50メートルの降下が楽しめる読売大落下傘塔が開設された。戦後、江ノ島に移築され昭和 26年(1951)「読売平和塔」のちに「江ノ島展望塔」となった。平成15年(2003)に解体された。
昭和19年(1944)戦時下の為、玉川遊園閉園(第一)、読売遊園も休業
昭和29年(1954)東急不動産により「二子玉川園」として再開
昭和60年(1985)閉園
地区内の「電停」と玉川遊園地
瀬田停留所=現在の瀬田交差点付近、遊園地前停留所=現在の身延山別院前バス停付近、玉川駅=世田谷初のターミナル駅となる(大井町線の開通以降)。
玉川遊園地(たまがわゆうえんち)登場
玉川電鉄は、旅客獲得のため玉川神社の下に約1万坪の敷地(長崎氏の初期の移住地、下耕地)を借りて、瀬田~玉川間に「遊園地前」停留所をつくり、園入り口まで桜並木を通している。滝の落ちる池や藤棚、ブランコ等の遊具を配置し、猿・孔雀・鹿などの小動物を飼い、会社の運動会などに利用できる運動場を設け、高台の「玉川閣(ぎょくせんかく)」という百畳敷の演芸場で芝居や浪花節会などを催していた。ここから見られる富士山などの素晴らしい眺めも評判を呼んだ。その後、昭和7年(1932)に日暮里にあった妙隆寺をこの場所に誘致し、身延山関東別院玉川寺として開山。最寄りの停留所名も「遊園地前」から「身延山別院前」に改称され、遊園地も太平洋戦争の激化により昭和19年(1944)に休止し、戦後は再開されることもなく住宅地となり、現在は、身延山玉川寺のみ残されている。

「玉電」事業の3本柱
貨物輸送事業
「玉電」は当初、多摩川の砂利輸送が中心で「ジャリ電」と呼ばれ、計画では「採掘販売」も想定していたが、渋谷駅起点と玉川における積み込み場所の未整備で、販売事業は予定した収益が上げられず、明治44年(1911)大丸組と責任販売協定を結び委託した。
砂利は単なる貨物となり、旅客輸送に注力できるようになった。貨物輸送事業の収益は旅客輸送事業と比較しても小さかったが、大正12年(1923)の関東大震災後の首都復興のための需要が増し、大量の砂利が幹線を経由して、東京市電気局線へ連絡輸送された。砂利輸送を目的に、大正9年(1920)に得た特許に基づいて、大正13年(1924)に砧線も開通、同線は玉電と多摩川砂利会社が共同で敷設したもので、砧線の大蔵駅から砂利が東京市電へ直送された。砂利輸送では、天現寺線と渋谷貨物駅を連絡する引込線が大正14年(1925)に設けられている。
貨物輸送事業は砂利に依存していたので、復興建設工事の完成と社会的な不況により、昭和5年(1930)頃には低調となった。
旅客輸送事業
収入の多くを占めた旅客に関して、大正5年(1916)年度下期の玉電の営業報告書は、「兎角天気廻り面白からず」と悪天候による行楽客の減少が営業に悪影響を与えたことを指摘しつつ、それでも乗客の増加を「遊客誘導に力を致したるの結果」と述べるなど、砂利を運ぶつもりの軌道は、実際には行楽客を運んでいた。
計画当初は砂利が八割、客が二割と見積られていたが、ふたを開けてみれば、明治42年(1909)年度の『電気事業要覧』によれば、旅客収入約6万円に対し、貨物収入は約1万3000円であり、旅客収入の方が八割となっていた。その他に電灯からの収入は1万円だった。
以上のことからも、行楽地、玉川の存在は強く意識され、「玉川電機鉄道の終点は鮎と蛍の名勝地」と新聞広告を打ったり、大正元年(1912)までに菖蒲園や玉川遊園地内に『小鳥猿鹿等を増飼し、兵庫島2000坪を借り入れ新たに遊歩場』を開設するなど企業努力が続けられた。玉川遊園地は大正5年(1916)には直営化し。更に大正11年(1922)には第二遊園地(諏訪河原)を開園したことは、玉川遊園地の恒常的な赤字を克服するため意味が含まれていたようです。大正14年(1925)には玉川プールやテニスコートを建設するなど、旅客誘引は多摩川河畔へ向かうような事業展開となって行く。

デハ200系。通称、芋虫・ペコちゃんと呼ばれた
路線の拡張
大正9年(1920)年代中盤は玉電の黄金時代で、大正11年(1922)からは不動産事業にも乗り出し(結果的にはさほどの規模にはならなかったが)、住宅のほか商店向けの貸家なども行っているほか、路線の拡張も進んだ。大正10年(1921)には世田谷の大地主・大場信續らが、地域の住民が玉電の支線建設のために土地や資金の寄付を行うことを申し合わせた承諾書を添えて、玉電に「電車線路延長願」を提出している。進む東京の拡大と郊外の人口増加に対し、地域の地主も住宅開発に積極的になっていた。これを受けて玉電も同年6月に下高井戸への支線の軌道敷設の特許を出願し、大正11年(1922)7月に特許を得て、大正14年(1925)に三軒茶屋~世田谷間が開通し、同年5月には世田谷~下高井戸間も延伸開通され現在の世田谷線が全通した。
大正13年(1924)には玉川~溝ノ口間の特許も取得し、二子の渡しには玉電も建設費52万円のうち15万円を負担して二子橋が大正14年(1925)完成、軌道と道路の併用橋により、昭和2年(1927)玉電は玉川~溝ノ口間が延伸された。溝ノ口には同年、南武鉄道(後のJR南武線)が開通していて、溝ノ口は連絡駅となった為、溝ノ口に近い七面山を「玉電の津田」が開発の手を加えた事から、現在でも七面山は「津田山」と呼ばれている。
昭和3年(1928)には渋谷橋~中目黒間が開業し、前年に開通していた東京横浜電鉄と競合関係になったが、東京西南方面では人口増加に伴い急速な交通網の整備が進んでいた。(後に、この競合関係が現、東急との併合につながる一つの要因となる)

左:デハ60型車両 中:吉沢橋を渡る 右:砧線跡を記念する?石像
バス事業に乗り出す
昭和4年(1929)米国で世界恐慌が始まり、翌年には日本も深刻な昭和恐慌に陥って、玉電の事業の柱である軌道旅客収入は昭和5年(1930)年度から減少し、これは昭和9年(1934)年度まで続くことになり、配当率も年々引き下げられて、昭和8年(1933)年度上期には6%にまで落ち込んだ。
軌道旅客収入の不振は、恐慌だけでなくバスの台頭が挙げられ、そこで玉電もバスに着目し、昭和2年(1927)に道玄坂~新町間の営業を開始し、昭和4年(1929)には中目黒線、新町のバス路線を玉川まで延長、昭和5年(1930)には日東乗合自動車の世田谷の路線を譲り受けるなど拡大し、昭和8年(1933)年度には全収入の1割余りを占めるまでに成長した。恐慌で落ち込んだ軌道旅客収入を補う重要な役割を果たした。
慶応閥主体の経営
電力供給のみならず出資を受けていた富士瓦斯紡績が、大震災の被害や社長の急死などから玉電への出資を引き揚げることになり、専務の津田興二は富士瓦斯紡績の持株を千代田生命へ肩代わりさせた。昭和4年(1929)の玉電の大株主は、内国貯金保険・日本徴兵保険・千代田生命が約2万株ずつを持つ主要株主となった(総発行株数は25万株)。
新たな出資者となった保険各社は、電気鉄道事業を格好の投融資対象と捉えていた。津田が同窓である千代田生命の門野社長に懇願したとされているが、千代田生命は「門野社長以下、一人の異学閥をも交えないオール・ケイオウ」という会社であり、玉電側は同社から支配人を受け入れている。これによって玉電は「三田出」の同窓で経営されていると評されることとなった。
大正時代の株主名簿には、徳川達孝(水戸徳川家)、森村開作(ノリタケカンパニー)、川崎栄助(川崎財閥)という瀬田にお住いの方と思われる名前も見られる( )内は推定。
瀬田から「行楽の玉川」へ移行
玉電が開通し交通機関が便利になるにつれて、二子橋付近から下野毛にかけては、東京市民の憩いの場として大いに賑わうようになった。大正時代に入ると、夏は多摩川堤の桜の花見や、二子玉川園近辺の大桃林やツツジ見物、初夏は蛍狩り、夏は花火大会や川遊び、そして秋はお月見と、四季それぞれに大勢の人々を集めるようになり、旅館や料亭もこの流れの中で増えていった。
特に玉川が一番賑わったのは、アユ漁が解禁されてから夏にかけての時期で、屋形船が何十艘も川面に浮かび、獲り立てのアユを肴にして、夜遅くまでお酒を飲んだり、三味線や太鼓を楽しむ光景が見られた。屋形船は、大正8年頃、4~6人で10円ぐらいで利用でき、下野毛村の漁師の貴重な現金収入だったといわれているが、直接的な現金収入の獲得は。地域発展の一里塚となったように思える。
玉電が産みの苦しみを乗り越えて、地域に定着できたことが、この後の「二子玉川発展」の約束手形だったことは疑いようのないことで、地域の歴史に深く刻印されるべきことと確信する。
「多摩川」を挟んだ二つの村 =参照サイト・資料=
ウィキペディア 高津区由来 滋味コフン 古墳なう 川崎市 中原区・高津区・宮前区の町名の移り変わり 高津物語、府中県道川崎歴史ガイド 大山街道ルート 再発見高津区 ぶらり歴史散歩 世田谷区 玉川三業地報告書 ふるさとを語る 地名の由来(瀬田・玉川・用賀・上用賀・玉川台) 瀬田 玉川町史 蘇った古民家 玉川神社由緒 世田谷区ホームページ 慈眼寺由緒 御朱印・神社メモ 日本遺産 ポータルサイト 玉川電機鉄道の設立と展開 三科仁伸 東急100年史 地理院地図


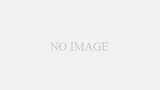
コメント