兄を乗り越えた「玉川」の総合力
玉川の名称に関する考察
河の名称としては狛江市中和泉4丁目、「六郷用水」の取入れ口付近に所在する「玉川碑(万葉歌碑)」に、万葉集巻14の東歌の一首「多摩川に さらす手作り さらさらに 何そこの児の ここだ愛しき」が刻まれている。又、別の歌には「多麻河」という表現が見られるそうだ。
「玉川碑」は元土佐藩士の平井薫威(しげたか?)が、地元の名主宅に逗留していた文化2年(1805)に建立、多摩川に近い場所だったので文政12年(1829)の多摩川の洪水によって流失したが、時は流れ、幸い松平定信(さだのぶ、白川藩主)揮毫の拓本が見つかり、定信を敬慕する人つながりで渋沢栄一の助力が得られ(講演と資金援助、全体の4割強)、大正13年(1924)に現在地に再建された。
私が注目するのは、何故、多摩川ではなく「玉川」という名称を碑に付し、のみならず「陰記(いんき、裏面の銘文)」でも玉川を用い、更に再建前の大正11年に渋沢栄一が起草した「撰弁書(せんべんしょ、碑を作った当事者の文)」では、川名、地名、会名など全てが「玉川」となっていること。どうやら玉川は、渋沢栄一が地元人ではないことを考慮すると、地域では一般的な名称だったようで、和歌で詠まれている「多摩川」の場所はその内容から当地に違いないと、平井薫威かあるいは大正の再建に携わった人らは断定したのかもしれない。
「玉川」は大蔵から始まる
「石井至穀(しこく)」は大蔵・鎌田の名主の家柄で、4代前の祖先には江戸内で唯一といわれた「大名」喜多見氏の庶子(しょし、本妻以外の子)を養子に迎えている名門の跡継ぎ。至穀は努力を重ねて徳川幕府の幕臣となったが、喜多見家との関係や4代前の当主、兼重(かねしげ)が、元禄3年(1690)当地に初めて玉川という名称の「玉川文庫」を創設し、その88年後に生を受けた「至穀」は文字通り書物に囲まれて成長した。世田谷で最初の図書館と言われ、それを有効活用し出世するという偉人伝風の筋書きも見逃せない。
兼重が「玉川」の名称を採用した理由は定かではないが、古い文書に「多摩川」の美称に「玉川」があったということから、「家塾菅刈学舎」を起こし玉川文庫を併設するぐらいの教養人には、選択の優先順位が高かったのかもしれない。
2番目は中町・等々力
明治8年(1875)中町・等々力地域に「小学玉川学校(現玉川小学校)」が開校した。荏原郡の中では「小学荏原学校(現若林小学校)」に次いで2番目の開校で、荏原学校は一番目の特権か郡名の「荏原」を採り入れる。その伝で言えば、適当な地名が無い状態で、しかも上野毛、瀬田、用賀等の複数の区域に跨る場合の校名選択は難しいのは当然で、額を集めて侃々諤々の議論の上(想像)、約200年前から地域にあった前述の「玉川文庫」の名が思い浮かんだような気がする。(普通に「多摩川」では味わいが薄いと考えたかどうか)
その後、明治22年(1889)の市町村制の施行により、それまでの奥沢・尾山・等々力・下野毛・上野毛・野良田・用賀・瀬田の8村が合併して「玉川村」が成立した際には、村名に関する瀬田村と等々力村の対立があり、地域の学校であった「玉川小学校」の名前を採用することで妥協がなったという例もあり、人々が有する愛郷心のようなものは、土地に根付いて生きている時間が長いほど愛着が増すのだと言えなくもない。
そして長崎氏の存在
地域第一の有力者、瀬田「長崎氏」についての勝手な想像でこじ付けですが、私は瀬田の長崎氏が、鎌倉幕府執権北条氏の内管領長崎氏と遠縁で連なるという風に見ている。北条氏の本拠地「現、伊豆の国市」には、伊豆急原木駅近くに「長崎」という地名があり「長崎神社」も存在している。そして直線で約2㎞の所に名水で有名な「柿田川湧水群」があり、その公園に沿って「駿東郡清水町玉川」、並ぶように国道1号線沿い三島方向に「三島市玉川」が存在する。1100年代の鎌倉時代、1500年代の後北条氏の時代に地名として存在していたかは不明(駿東郡の玉川村が幕府旗本領との記録あり)。私の推測は村名決定に際して、祖先の地の「玉川」が念頭に去来したのではないかと推測している。
夢の学校 玉川学園
「小原國芳(くによし)が、私立成城玉川小学校を開設するときに、牛込にある成城小学校と区別するために「玉川」の字を用いた。近接する「多摩川」を意識したが、江戸時代の刷り物にも、この地域を「玉川」と呼んでいたことから「わかりやすく、書きやすい、感じがよい」という理由で使用した。その後、成城小学校は砧に移転し、成城玉川小学校を併合、玉川の名前は消えた。
一方、全人教育を目指した夢の学校=「玉川学園」は小田急線の沿線の丘陵地にあっても、変わることはなかった。」(昭和4年(1929)設立)(小原國芳さんの説には納得させられるものがある)
周辺では「多摩川」も採用されている
大田区に第二京浜国道と環八が交差する東南側辺りの地名を「多摩川」とし、マンション名では丸子多摩川、東急多摩川線「多摩川駅」付近は圧倒的に「田園調布」冠が多いが、蒲田方向へ向かうと鵜の木辺りを境として沿線のマンションに多摩川名が増えてくる。又、狛江にも和泉多摩川駅がある。
地区内でも、多摩美術大学(上野毛)、多摩川テラス(瀬田)、ドエル多摩川(上野毛)、多摩川ハイツ(大蔵)、グレース多摩川・マリオン多摩川(鎌田)、多摩フラット(野毛)などが、グーグルマップで確認される。
玉川の行政区割りの変遷
★明治22年(1889)奥沢、尾山、等々力、下野毛、上野毛、野良田、用賀、瀬田の8村が合併して「玉川村」となり、各地区はそれぞれ大字となり「瀬田村」は大字瀬田となる。
★明治45年(1912)府県境界の変更があり、多摩川右岸にあった区域は神奈川県となる。
★昭和7年(1932)10月 世田谷区成立時に、玉川村大字瀬田の区域は次太夫堀を境として、北側が玉川瀬田町となり、南側の上耕地、中耕地、下耕地、根耕地、提外、向河原が新設の玉川町となる。
現在、二子玉川地域以外で残る玉川の地名としては、近隣に玉川田園調布と東玉川の2ヶ所あるが、かつての「玉川村」が整理されていく中で分散し残ったものと言われている。(玉川中町公園、玉川野毛町公園にも残されている)
玉川地域の先見性と独自性
昭和22年(1947)東京35区の統廃合の時に、旧・板橋区の中で、西部の練馬地域が独立を求めたのに倣い、再び世田谷区から 「玉川区」として分離独立を主張、都に建議書を提出。(1回目は昭和7年(1932)世田谷区成立の時)当時から広い地域だったので、きめ細かい行政が期待できないという思いが住民にはあり、それが正に慧眼で今日90万人を超える「大区」となって、動きが鈍く身を持て余すような現状を見通していたようだ。住民の運動は実現しなかったが、今でも旧玉川地域民が有した世田谷とは同化したくないという無意識が現存する。玉川地域の独自性の例を挙げる。
●玉川地域には「世田谷」と冠した公共施設がない。
●医師会は玉川地域のみ「玉川医師会」であり、他の地域は「世田谷区医師会」。
「玉川医師会は、昭和27年に世田谷区医師会より分離独立して玉川医師会として発会し、平成25年に一般社団法人玉川医師会となった世田谷区の南側を中心とする医師会です。」
●薬剤師会は玉川地域・砧地域と烏山地域の一部が「玉川砧薬剤師会」であり、その他の地域は「世田谷薬剤師会」である。
●電話番号の3ケタ目は、玉川地域以南が700番。世田谷を含む4地域が400番である。
●衆議院選挙小選挙区の区割りでは、世田谷を含む4地域が「東京都第6区」であるのに対して、玉川地域は目黒区と共に「東京都第5区」である。(少し古い情報、区割り変更で多少変わっているかも知れない)
第一の推進力「玉電」が選択した「玉川駅」
この地域の大正の時代の地名は「玉川村大字(おおあざ)瀬田」であり、小字(こあざ)?では「中耕地」「瀬田河原」などと呼ばれていた。玉川村は奥沢までの広域な村で、現在の玉川地区は「崖下」の辺境地(村の端っこ)で農地ばかりであり、こうした状況でも明治40年(1907)玉電開通に際し駅名に「玉川駅」を採用するが、単純には玉川村の中で初めての鉄道駅であったからといえなくもないが、辺境地が村の中心になる(する)という予感(決意)があったような気もする。 因みに、この辺境地が正式に「玉川」という地名になるのは、昭和7年(1933)世田谷区が成立した時で、この時の合併8町村はそのまま町名に「玉川冠」を暫く載せていたが、新設の形となった「玉川町」は玉電の予感?の如く一人、独立した町名となっている。
味わい深い公共施設の命名
二子玉川駅 玉川福祉事務所 二子幼稚園(東京都市大)
二子玉川公園 玉川ボランティアビューロ
二子玉川ライズ 玉川税務署
二子玉川地区会館 区立玉川3丁目住宅
二子玉川小学校 玉川歯科医師会
二子玉川緑地運動場 玉川高島屋
二子玉川社協 玉川高校(昭和30年創立)
玉川病院(瀬田にある)
大雑把に言うと比較的に古い施設は「玉川」、新しい施設は「二子玉川」ということのようだ。二子玉川小学校は順当なら「玉川」小学校となるところ、創立から80年(令和3年)でも、等々力には148年の「玉川小・中学校」があり、如何ともしがたい。
「玉川高島屋ショッピングセンター」と、後から出来た「二子玉川ライズショッピングセンター」の違いも、基本は古さの違いとみて間違いないが、いずれも二子玉川という名称が普及し駅名も定着している中、高島屋が意識したのは「玉川」という地元であり地元重視の姿勢の表れ、そして簡素かつ美しい調べを採用、「ライズ」は開発の中心「東急」の二子玉川成長戦略をそのまま形にしたのだと概観する。
驚異の大発展 「玉川」に力が集積した
第一段ロケット点火=玉川電気鉄道=
大正から昭和初期にかけて風光明媚(めいび)な観光景勝地として多くの人を招き入れた。目の前に一級河川の多摩川が流れ、後背地の国分寺崖線(がいせん)には緑豊かな丘があり、富士山も望める絶景の場所で、崖線沿いには政財界の著名人たちの別荘が建ち並び、川沿いには料亭が軒を連ね、目の前で釣れる鮎などを供し、舟遊びをするといった風情のある光景が見られた。
玉川駅は、明治40年(1907)に開業した通称「玉電」と呼ばれた玉川電気鉄道玉川線(後に東急電鉄に買収される)の終点駅となった。渋谷から直線で約5kmだが、路面電車でゴトゴト揺られて来ると郊外へ来たという思いも強くなり、瀬田まで来て国分寺崖線の崖上から滑るように下る見晴らしの良さ、爽快感は体験者の古い記述で語られる所だ。
途中駅ではなく終点になった事が天啓であり、後に東急が大井町線を引き込んで新たな終点駅ができると、小さな砧線と合わせて地域初の「ターミナル駅」が誕生する。通過駅と違い、終着駅は人・物・金が集積し発展の基盤が形成されることとなった。
「五島慶太」が命名?=二子玉川=
二子新地の賑わいに目を付けた目蒲の五島が、大井町線の終点の駅名に二子を付けて地域的な発展(集客)を企図したと言われている。しかし、五島の「目黒蒲田電鉄」は昭和2年(1927)に大井町線(大井町~大岡山間)を開通させ、その先の「二子玉川」を目指していた。と言うのも交付された免許では当初(奥沢~瀬田河原間)の「二子玉川線」と記載されていて、大正13年(1924)の申請時点で、すでに五島の頭には「二子玉川」の四文字があったということであり、二子玉川という名称は五島の開発意欲から生まれたと言えそうだ。
玉川駅と二子玉川駅の並立、そして統合
目黒蒲田電鉄の工事は順調に進み、昭和4年(1929)11月二子玉川線(自由が丘~二子玉川間)、12月(大岡山~自由が丘間)も開通し、大井町線「二子玉川駅」が開業した。その後、企業体にも変更があり、昭和13年(1938)「玉電」が「東京横浜電鉄」に併合され、更に昭和14年(1939)「目黒蒲田電鉄」が「東京横浜電鉄」と合併し商号を「東京横浜電鉄」とし、長きにわたり地区に馴染んだ「玉電」は消え、後に社名が変わる「東急」に二子玉川の鉄道は集約されて、ターミナル駅の輪郭が出来上がった。
慶應義塾から東京帝大出身官僚へ
「玉電」は地元有志が起業し、いくつもの困難を乗り越えながらのたうち回った印象がある。その後加わった東京信託・慶應義塾グループが奮闘したといえども、主目的である砂利採掘・販売事業の躓き、誘客招致のために他方面の投資など負担も大きく、その間、景気の悪化も直接経営に影響した。こうした状況を見極め、渋谷で競合関係にあった「東京横浜電鉄」の五島慶太が株主として参入し、千代田生命から入社した鵜飼重雄支配人に友好的買収を申し入れ、拒否されたあとは、大株主を説得して回り持ち株を買収し、昭和13年(1938)吸収合併を果たして経営陣を刷新、経営陣の大多数が東京帝大・鉄道省出身者となった。
地元有志が、地元のために作った鉄道会社は「二子玉川」の発展に大きな足跡を残したが、渋沢栄一から五島が引き継いだ、総合的な視点には及ばなかったようだ。歴史に刻まれる30年の奮闘だった。
目黒蒲田電鉄=五島慶太登場=
明治・大正期の大実業家であった子爵渋沢が、自然と都市生活が調和した「田園都市」を建設することを目的に田園都市株式会社を設立。その4年後の大正11年(1922)鉄道事業部門を五島慶太が引き継ぎ「目黒蒲田電鉄」が発足。この会社が合併や社名変更などの変遷を経て、現在の東急になる。経営の変わった「玉川駅」は昭和14年(1939)「よみうり遊園駅」と改称し、昭和15年(1940)にはよみうり遊園駅と二子玉川駅を統合して「二子読売園駅」となった。
当初、東急は遊園地事業より路線の開発に力をいれていたが、周辺の宅地化が進み建物が増えたことで、生活排水が多摩川に流れ込み川も汚れて鮎も釣れなくなると、景勝地としての価値に影響が及び、新たな都市住民のためのレジャー施設として遊園地事業に注力する。昭和29年(1954)駅名を「二子玉川園駅」に改称、二子玉川園の名で一世を風靡した郊外型レジャー施設の街に変貌させた。
第二段ロケット点火=玉川高島屋ショッピングセンター=
料亭も三業地も雑多な歴史の一つとして埋もれようとする時、更に、東急の態勢が整わず新たな構想が芽を出す前、突如、無骨な男たちが汗水流し紡いでいた発展の試みのど真ん中に、白鳥か白鷺が舞い降りるかのように「玉川高島屋ショッピングセンター」が西口駅前に登場した。高島屋の登場は間違いなく新たな開発の方向性を再提議し、街に高級感と優雅さを感じさせるようになると、辺境の地の場末感は一掃されて行った。
ここで見逃せないことは、第二段ロケットの点火の役割としては東急の玉電への参入が欠かせず、玉電の窮地を救った電気事業も東急の路線延長の努力のお陰で人口が増加しているという側面と、玉電と大井町線の「ターミナル駅」という集客の両足がしっかりしたからこそ、高島屋(東神開発)の二子玉川進出が実現したことは疑いようがない。ただ、そうだとして衆目の一致する感覚は、先に目に見えた物を認識することになり、高島屋の登場で東急の「五島昇(慶太・長男)」が歯噛みしたという「噂」にも心に留めれば、一旦裏方に回った形の「東急」には、最後の宇宙船切り離しという極点、「二子玉川ライズショッピングセンター」の開発者という名聞が残されている。
高島屋が変えた=二子玉川=
高島屋は飯田新七(文化2年(1805)~明治7年(1874))が、京都の丁稚奉公から身を起こし、天保元年(1830)古着専門店を開店。義父の出身が滋賀県高島郡の出身であることから屋号を「高島屋」とした。バラの花をイメージフラワーとして採用し、現在も包装紙などに使われている。「日本で始めての郊外型ショッピング・センター」と見なされている玉川高島屋SCは昭和44年(1969)に開業。高度経済成長が終わりに近づこうとする時期に、田園都市計画による郊外開発と、それにともなう郊外住民の増加と生活様式の変化を受けて誕生した。「銀座のお買い物を玉川で」をテーマに、高島屋百貨店と125の専門店が揃い高度経済成長の波にも乗り、世田谷区をはじめ広い商圏内に居住するようになった富裕層を相手に、非常に良質で高感度な商業施設を運営した。
大切にした地元対応=反対は無かった?=
用地取得に直接関りがないとしても、こうした大規模開発には地元への配慮が欠かせないのが通常であり、高島屋予定地近くの「二子玉川商店街」と、駅東口の「玉川商店街」の各商店会長や町会長方にあいさつに回ったところ「高島屋さんと銀座のお店が来ることに異論はない」とあっさり受け入れられて、担当者が拍子抜けしたという逸話もある。
地元の商店街では、事前に世田谷区役所の経済課長などと相談していて、「鴨がネギをくわえてくるようなものだから受け入れないと損だ」ということで意識統一がなされていた。さすが、玉川の地元民は開明的であり、高級店が来ても地元商店との競合はあり得ず、それよりも高島屋に大勢のお客が来れば、地域への何らかの波及もあるという計算がなされていた。とかく大規模開発などというと功利や無知から騒動となる例が多い中、玉川地域が冷静に対応できたことが二子玉川地区にとり最大の僥倖であり、地域への波及には時間を要したものの「高島屋裏のレトロな商店街」は健在で、新規出店も続いている。今日、高島屋も商店街のメンバーとなり、街の各種行事に東神開発は欠かせず、当に「完全な一対一の共存共栄(高島屋の運営理念)」がなされている。
東急が腹に収めた計画
「二子玉川という立地が持つ可能性を東急は早くから認識していた。駅の西側の5万坪ほどの土地(二子玉川園・東急自動車教習所)を、ハワイのアラモアナ(SC)のようなものにする。しかし、当分新玉川線(地下鉄)と田園都市線整備に忙しく、あと10年ぐらいは手が出せない。それまでの間に精々お客さんを集めておいて下さい」という腹の内を高島屋に示している。これが想定以上の時間を要したが、二子玉川第三形態への進化「二子玉川ライズショッピングセンター&レジデンス」に繋がる。その意向を汲むかのように、高島屋も最盛期で年間1,000億円を超える売上を叩き出し、怪物ショッピングセンターのブランドを築き上げ、ライズの完成を迎えた。結果的に‘23年度の両館合わせた年間来館者数は4,000万人超となり、二子玉川の知名度、人気は飛躍的に上がっている。
二子玉川大変貌 東急の底力
二子玉川東地区第一種市街地再開発事業(計画)
面 積 :約11.2ヘクタール
事業費 :約1,370億円
施行期間:平成12年度〜平成22年度
当初、10年の工事期間を見込んでいたものが、経済状況の影響等で完成まで30年を要した。二子玉川の平成の記憶は、ライズ一色だったと言っても大袈裟ではなく、計画には旧来の地元住民も参画していたが、地域には新たな住民も多数増えそれが変数となり、高島屋開業時には見られなかった反対運動が起こった。東急に対するある種の怨念のようなものが底流に感じられ、想定外の負担を背負ったことは特筆される。反対論は住民に不安を与える俗論のような議論も多く、出来上がってみれば「そんな恐ろしい化け物」ではなかったことは直ぐに分り、運動は事業の進捗の中、尻すぼみ自然消滅したようだ。
平成23年(2011)かつて遊園地があった場所に、第三形態の「真の怪物?」が登場
二子玉川ライズショッピングセンター&レジデンス
「二子玉川ライズ」は駅に近い方から「ドッグウッドプラザ」、「ステーションマーケット」、「リバーフロント・オフィス」、「タウンフロント・オークモール」、「バーズモール」、「テラスマーケット」、「ホテル・クリムゾンハウス」、「アネックス・スタジオホール」、「タワー&レジデンス」、「プラザモール」で構成され、多様な組み合わせで複合的な空間が実現した。
「ライズ」を象徴するコンセプト「水と緑と光」のイメージを表現したテラスマーケット地区は、「ライズ」全体の3分の1のスペースを施設の中心に据え、それぞれの屋上にルーフガーデン(3ヶ所)を施し、間を抜ける「リボンストリート」の通路を含め、可能な限りの緑化がなされている。
ルーフガーデンの中心は、「蔦屋家電・109シネマズ」の入る建物で、5~6階相当の建物の屋上には、大きな芝生の「原っぱ広場」があり、多摩川面には展望席、光り輝く川面や富士山の全容、鉄橋を渡る東急電車等をゆっくり見ることが出来る。芝生スペースは子供たちが遊んだり、イベントができる場所で、私の数少ない体験としては「クリスマスライトアップ」と「薪能」がある。
原っぱ広場の西北側に石組があり、そこからポンプで汲み上げた「せせらぎ」が流れ出し、北東側の端から下の階に流れ落ちている。落ちた先は「めだかの池」で、もうかなり緑が充実した「ビオトープ」。カルガモが子育てをして、親子が多摩川へ移動するのが話題になったこともある。職員に見守られながら、親子が階段を降り、リボンストリートを経由し、二子玉川公園の「スタバ」の横から多摩川を目指す光景は、ユーチューブでも公開されている。(隼か何かが小鳥を襲うとか何とかで、残念ながら最近は見られなくなった)
楽天クリムゾンハウス
日本興業銀行(現みずほ銀行)出身の三木谷浩史氏が、平成9年(1997)に起業したECモール運営会社・株式会社エム・ディー・エムを起源とする会社。ECモールの名称に使用し、平成11年(1999)には商号にも用いた「楽天」は、安土桃山時代の楽市・楽座のような、人々で賑わう市場をインターネット上に作りたいという想いと、明るく前向きに「楽天」的に行きたい(楽天主義)という想いが込められている。
平成27年(2015)より、グループ企業を集約し効率化を図るため、二子玉川ライズにある新社屋「楽天クリムゾンハウス」の地上2階から27階(隣接する楽天クリムゾンハウス アネックスの3階・4階も占有)に移転した。
豊かな自然と別荘文化と住民力
駅を挟んで東西に大型ショッピングセンターが並立することで共倒れの心配も聞こえていたが、高級な商品サービスは高島屋、形式ばらない日常生活のサービスを東急が担うという「すみ分け」ができ、ライズには商業以外のオフィス、シネマコンプレックス、ホテル、スタジオなどが出来、衛星都市化していた街にショッピングだけでなく、仕事で毎日たくさんの人がやって来るという大転換が起き、あらゆる心配は杞憂となった。
ライズの開業によって住民数、来街者数、就業者数が増え、二子玉川全体の市場規模も大きくなり、またライズ開業後も玉川高島屋の改装の努力は続き、双方切磋琢磨して全体の街の魅力は増し、顧客の選択の幅は広がっている。
二子玉川地区は昭和7年(1932)風致地区に指定され、開発規制がかかり環境の維持・保全がなされている。時代が進み人口増加を受け入れる中で、空地は住居となり、マンションとなって街の様相が大きく変化しても、厳しい基準の中で最大限の環境整備がなされている。個人住宅でも可能な限りの植栽がなされ、住民の環境を保とうとする意欲は強い。崖上の元別荘地も形は変わっても樹木や雰囲気は残り、環境保全の一助となっている。
こうした土地に進出した高島屋は、当然というか率先して緑化に励み、単なる郊外型ショッピングセンターのような実利主義には陥らず、全館緑を感じさせる取組みを継続している。利益あってのことだとしても、緑化の考え方には利益度外視の執念も感じられる。地元に溶け込み、更に環境を創造し、土地の価値を高める努力が続く。後発のライズも全く遜色のない環境創造の場を実現している。
このように国分寺崖線と多摩川に挟まれた「箱庭」のような二子玉川は、環境・住民・事業者の三位一体による「来て良かった。又行きたい。」街づくりが今も進行している。
東急の努力は続く
二子玉川終点だった大井町線が昭和38年(1963)に田園都市線に改称した。昭和41年(1966)に田園都市線の専用鉄橋ができ二子橋から分離され、同年に長津田まで延伸した。玉川線が国道246号の交通量の増加で昭和44年(1969)に廃止となり、昭和52年(1977)に新玉川線(地下)が渋谷・二子玉川間で再スタートする。昭和54年(1979)新玉川線が田園都市線に変わり半蔵門線と直通運転となり、同時に大井町線の名称が復活し、大井町線は再び二子玉川駅が終点となった。平成21年(2009)複々線化により大井町線は溝の口駅まで延伸された。令和元年(2019)一部急行車両が、田園都市線に乗り入れる(中央林間駅まで)。
こうした弛まぬ路線整備により、二子玉川ライズ開発前の平成22年(2010)の二子玉川駅の乗降人員が約10万人強/日だったの対して、平成29年(2017)の乗降人員は約16万人/日。私鉄の駅でここまで短期間で乗降人員が増加する例は滅多にないようだ。
兄を乗り越えた「玉川」の総合力 =参照サイト・資料=
ウィキペディア 狛江市教育委員会 東急100年史 ぶらり歴史散歩 東京の地名の由来 東京知ったかぶり 世田谷区ホームページ 玉川学園 玉川の由来 グーグルマップ 玉川高島屋 二子玉川の再開発過程―調査報告 二子玉川ライズ 多摩川両岸の地形や土地利用からの考察 玉川医師会ホームページ


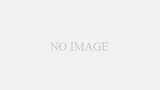
コメント